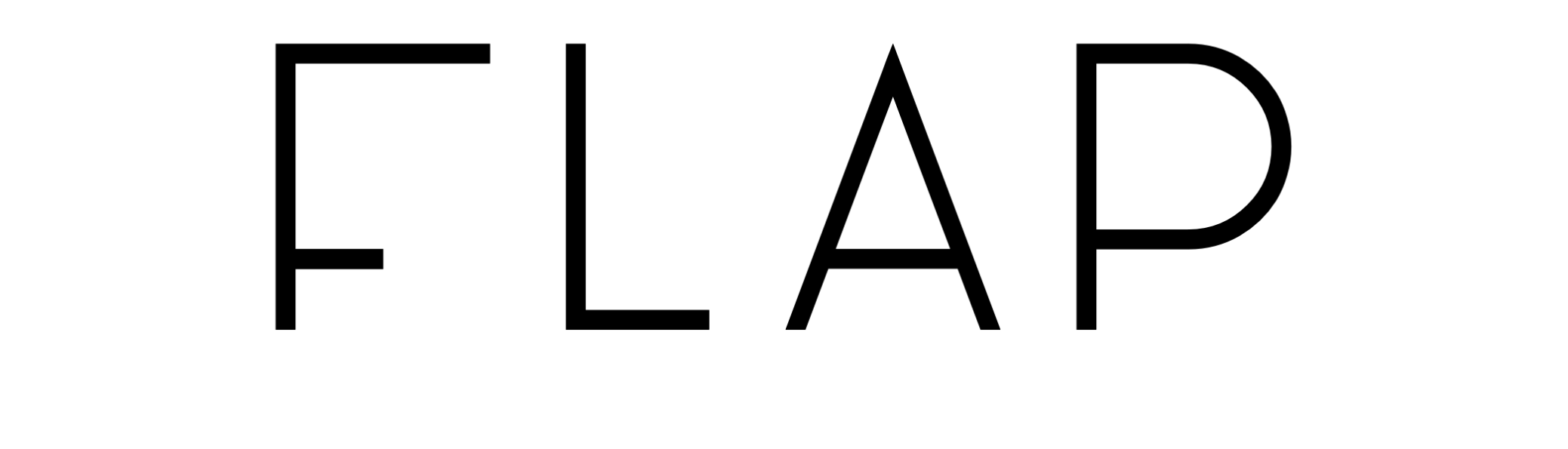意識低い系がMITに行くまで

そのままびゅーんと行ってしまえ。
付随する概念を取り除いたフラットな環境を想定し、自分の中に「留学」を落とし込んだ結果、留学するべきという結論が出たのならば、とにかくがむしゃらに突き進んで欲しい。
語学力だのお金だの卒業時期なんてものは本当に大した問題ではない。
いくらでも手立てはあるのだ。
プロフィール

名前 中畑 育歩 :留学開始時の学年
修士1年 : 留学開始時の所属
物質理工学院 材料系 材料コース
基本情報
留学プログラム :私費長期留学
留学先 :アメリカ・ボストン
所属先 :マサチューセッツ工科大学
留学時期 :2018/10/01~-2019/08/31
留学期間 :11ヶ月
過去の留学経験 :超短期派遣プログラム@フィリピン
総費用 :~300万
奨学金 :あり
奨学金名称 :トビタテ!留学JAPAN
受給金額 :準備金25万円 +(月16万円 × 11ヶ月)= 201万円
卒業時期: 1年遅れた
留学の動機
※ 昨年のシンポジウムの記事が上手くまとまっているので、詳しくはそこを見て欲しい。
留学に行こうと思った最初のきっかけは、高校生の時に語学研修としてカナダに行った時。頭の中で当たり前に分かってはいたことだが、全員が日本語じゃない言語を話していることに衝撃を受けたことを覚えている。他にも文化の違い(公共の場でもすぐ脱ぐとか)や価値観の違い(車がガンガン信号無視するとか)を目の当たりにし、ワクワクが止まらなくなり、帰る前日の夜にホテルの一室で1人でガッツポーズをしながら、「俺は将来海外に行くんだ」と強く決意したのを覚えている。
そこからはシンポジウムの記事にもある通り、大学入学と同時に周りのレベルの高さに絶望を感じざるを得ずに、一年生の後期は週に多くて二日しか学校に行かない生活を続けていた。二年生になり自分を取り戻し始め、その勢いのまま三年生になる直前の春休みに、フィリピン超短期派遣プログラムに参加した。フィリピンでの十日間は毎日フルスケジュールで疲労度マックスだったにも関わらず、毎日のように何本も何本も”RED HORSE”という麦酒を飲み重ねていた。必然的に毎日のように数分のちょい寝坊者が出て、先生を怒らせてしまったのは今となっては良い思い出ということに勝手にしている。
三年生になると、一年生の不真面目ぶりからは考えられないが、奇跡的に研究室への早期所属のチャンスが巡ってきた。この機会を使わない手はないと考え、研究室に早期所属するとともに、指導教員の先生と留学の計画を立てた。結果的に、学部三年半の早期卒業、一年間の休学、一年半の修士課程修了、という無茶苦茶なプランを立て、実行することにした。
当時は研究方向(博士課程や企業の研究職)に進むか、それ以外の方向(所謂文系就職)に進むのか迷っていた。そこで、とりあえず自分の研究分野でトップレベルに行けば何かしらわかるだろうと思い、材料工学で世界一位のMITに行くことを決めた。しかし当時は、東工大にはMITとのコネクションがなかった(現在は交換留学プログラムがある)。そこで、興味のあるMITの研究室をググり、自分を嘘のない範囲で最大限盛り、指導教員の推薦書とともに向こうの教授に直接メールを送った。人生で一番ではないかというくらい幸いなことに、向こうの教授からSkype面接をしないかという返答があった。喜びのあまりウキウキしすぎて何の対策もしないままSkype面接に挑むと、通信環境も悪いし、英語も聞き取れないし、そもそも聞き取れても解答がわからないものだったりで、結果は散々だった。しかし、翌日に合格連絡がきた。皆さんもお分かりだろう。この申し込む過程で何が一番大事か。そう。自分を最大限盛ることである。
留学内容
MITの研究室にてチタン合金の破壊のメカニズムに関する研究を行った。金属金属ぅ。これは東工大での研究内容とは異なり、秘密保護なんとかの関係から、MITでの研究結果をそのまま東工大の修士論文に使うこともできない。ほんとこれだけは残念無念以外の何物でもない。
研究室には信じられないくらいの金属学オタクとか、家の場所を偽ってまでも学校に来たくないやつとか、逆に文字通りいつ行っても絶対にいるやつとか様々だった。ちなみに金属オタクと常駐野郎は同一人物だが、こいつは俺と席が隣だったこともあり、最初はこいつを見る度に焦っていた。本当にこいつは尋常じゃない努力家で、土日だろうが深夜だろうが早朝だろうが、必ず研究室にいて論文を読んだり実験してたりする。こいつが極稀に家に帰るときの捨て台詞は「今日洗濯しないと着る服がないんだ。でも二時間後に戻って来るよ。」だった。本当に二時間後に戻ってくるから怖い。
しかしそいつだけが特段目立つわけではないほどに、研究室全員の金属学に対する意識が高かった。研究室にいるだけでピリピリ感が伝わってくる時もあった。やはり噂以上に、アメリカの学生は日本の学生と比べて桁違いに意識が高い。
Visiting Studentという身分だったため、授業をとることは公式には許されなかった。非公式には教授に直で頼めば許されるケースもあったのだが、大してそこに対するモチベーションもなかったため取らなかった。
他にも日本祭りのボランティアなどもしたが基本的には上記が主な活動内容である。
留学で得たこと
※昨年のシンポジウムの記事が上手くまとまっているので、詳しくはそこを見て欲しい。
一番成長したのは間違いなく自炊力。渡航前は一度も実家から離れたことはなく、初めての一人暮らしが今回のアメリカであった。スーパーに行ってもどれが何の料理になるのか、そして「そもそもなんじゃこの野菜」というところから始まった。最初の一ヶ月なんてペペロンチーノしか作れなかったので、すぐに栄養不足で元気がなくなった。その後、少しでも野菜を取ろうと毎日せっせと炒飯を作っていたある日、自分が料理している時に24F建ての寮全体で信じられないほど爆音の火災報知器が鳴り、それ以降料理をするのが怖くなり引っ越した。それでも物価が高いボストンで生きていくために、自炊を最後までやり遂げたことはこれからの財産になると思っている。
他に挙げるとするならば、自分の価値観が変わったことである。様々なところで変わったが、特に変わったことは人とのつながりを今までの20倍大事にするようになったことだ。留学に行くまでは正直自分である程度なんでもできると思っていたこともあり、人に頼ったり、頼られたりすることの意味をそこまで感じていなかった。しかし、実際に現地に行ってみると、決して自分一人で出来ていたことじゃなかったんだと気付かされました。初日の夜から食べるご飯も寝床もない私にカレーと寝袋を恵んでくれたカナダ人のルームメイトや、実験がうまく行かず元気がない時に深夜1時からでも一緒にギターをかき鳴らしてくれるスペイン人のルームメイト、どんな時も自分の研究を手伝ってアドバイスしてくれる研究室のメンバーや教授、そろそろ日本に帰りたいなーと思う頃に知り合い始めた日本人たち。どんなところでも自分を助けてくれるのは、決して自分ではなくいつも周りの友人たちだった。これを機に私は人とつながっていることのありがたみを本当の意味でわかり、これからもっと大切にしていこうと決意した。
いやぁ、我ながら良い話をしたな。うん。
留学での思い出
数え切れないほどの思い出がある。上記の寮の火災報知器で心臓が止まりそうになった他にも、研究室で研究中にサイレンが鳴って心臓止まったり、友達と組んだバンド練習でイギリス人の友達は1時間遅刻するしインド人の友達は来なかったり、引越し先の風呂がありえないくらい汚かったり、そこのルームメイトが一切食器洗わなかったり。本当にキリがないほど思い出がある。(たまたま今あげたのが悪い思い出なだけで、良い思い出ももちろんたくさんある。)
一つ印象的で自分にかなり影響を与えたのは、日本人のYさんというMITの博士研究員である。彼は、私が留学してから半年経った頃に東大の博士課程を終えてボストンの地に突如として現れた。彼がボストンに来て二日後に開かれた日本人交流会では、異なる背景や価値観を持つ人々が集まり、飲み会にも関わらず熱く議論する人もいた。その中で、Yさんは現地移住歴が長いかのような口調で話し、「来て何日ですか?」「二日目です。」という受け答えによって大爆笑を取っていた。その場では、私は彼のことをただの面白い人だと認識していた。しかし後日、話していくうちに彼の中には、専攻に対する大きなプライドや、彼自身の中での大きな人生の軸があることが分かった。往々にして、人は尖りを隠すことができずに、触れにくい人間になってしまう。しかし、彼は内面で大きく尖っているが、それを完全に隠すことができたため、皆から愛017される人柄を獲得していた。その姿を見て、私は人生で目指す姿がはっきりと見えた。

氷点下の気温の中海に入る猛者たち(俺も猛者)

MITのど真ん中を流れるチャールズ川とヨット達

どこかの裏路地と紅葉

研究室のみんな

MITのメイン

一押しのバンドSummer Saltのメンバーとライブ後に
留学までの道のり

語学力
英語
TOEIC 700~795→TOEIC 800~895
留学中の苦労
学部一年の時の最初に受けたTOEICは545点。まあこんなもんだろうと思い、プライドが高かったこともあり大して勉強しなかった。その後たまたま学部二年の後半に友達とTOEICを再度受ける流れになり、ラーメンをかけて争った。その時は単語だけを二週間ほど勉強して735点取れた。ここで完全に調子に乗った。「あ、英語余裕やん。ちょいやればできるんかい。」と。MITの他にも実は派遣交換留学プログラムのETHにも併願をしていて(留学生交流課の方々には多大なるご迷惑をおかけしました。本当にごめんなさい。)、その際に必要だったTOEFL ITP 550点の語学要件を、ちょうど550点で乗り切った。それ以降は本当に英語を勉強しなくなった。MITへの留学が決まってからもそれは変わらず、直前になったら何かするかなと思ってはいたものの、全くしなかった。
しかし、いざ現地に行ってみると、それはもう、これは本当に英語なのか?と思うほどに飛んでくる意味のわからない言語に全くついていくことは出来ず、ボストンについて二週間ほど経ち、ここで話されている言語は英語じゃなくスペイン語ではないのか?いつからメキシコ(公用語スペイン語)に言語を侵略されたんだと真剣に悩む夜もあった。 それでも日常は過ぎていき、コミュニケーションしないといる意味もないどころか、文字通り生きていくことも出来ないので、死ぬ気で聞き取り、「世界の果てまでイッテQ!」でおなじみの出川なみの「オーイエス!」を連発しながらなんとか生き延びた。
ボストンについて三ヶ月間その生活を続けていると、ふとあることに気づいた。「お、俺人と話す時に緊張していないぞ。」と。今までは自分の圧倒的な英語力不足から、話すことすら嫌になっていたのに、英語能力の向上から人と話す際の緊張が減ったのである。そこからは日常の会話で困ることはなくなった。まあルームメイトの一人の英語は最後の最後まで何言っているのかはわからなかったが。そういうこともあるさ。
語学の面で困っている時に、幾度となく「あー留学来る前にやっとけばよかったなぁ」と思いかけたものの、同時に「あーどーせ時間が戻っても同じようにやらないんだろうな」と思い直した。そう。語学力で悩んでいるあなたも僕と同じように、コンスタントな勉強が出来ないタイプなのかもしれない。でもそんなことで留学は諦めて欲しくない。語学力なんて行ってからが勝負でしょう。行ってから初めて頑張るっていう手もあることをお伝えしたい。
留学を考えているあなたへ
※何度も言うが、詳しくは昨年のシンポジウムの記事を見て欲しい。
※あくまで個人的感覚であり、FLAPとしての見解ではないことを留意いただきたい。
決して全員に留学に行けとは言わない。強くおすすめはするが、自分の研究分野では日本が一番良い環境などの理由で、人によって留学の向き不向きというものがあることは否めないからだ。
しかし、全員に留学を自分に落とし込めと言いたい。留学は誰でもできる。そうあなたもできる。自分でも留学ができることを実感し、自分が自分の好きな国に留学に行っている姿を妄想して欲しい。留学に行くか行かないかを決めるのはそこからだ。英語ができないからって、経済力がないからって、留学が自分には遠いものだと決めつけるのは大いに時期尚早である。
付随する概念を取り除いたフラットな環境を想定し、自分の中に「留学」を落とし込んだ結果、留学するべきという結論が出たのならば、とにかくがむしゃらに突き進んで欲しい。
語学力だのお金だの卒業時期なんてものは本当に大した問題ではない。
いくらでも手立てはあるのだ。
行け。そのままびゅーんと行ってしまえ。
現役の科学大生にふらっとFLAPで留学について質問してみませんか?

✔︎留学帰ってきた先輩や留学中の先輩に進路のこと、単位のことなど何でも質問できます!
✔︎留学に興味あるけど何したらいいか分からない...といった質問でも大歓迎です‼︎🙌
👉 詳細はこちら